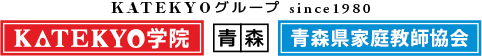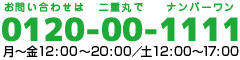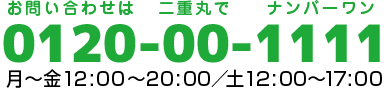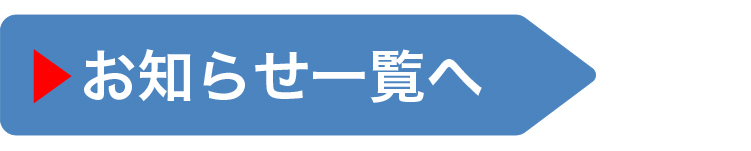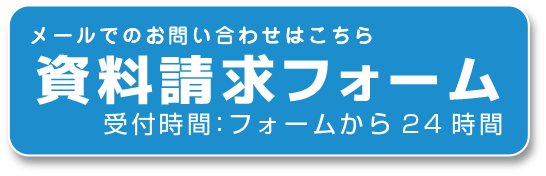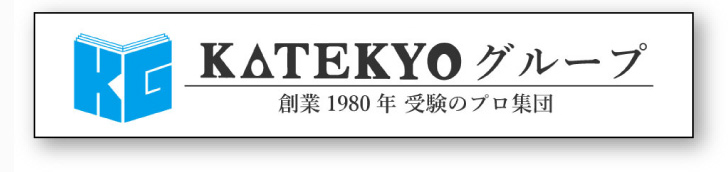KATEKYO学院青森からのお知らせ

2023年10月15日
小論文と定言命法②
青森県の皆さまこんにちは。青森県家庭教師協会・KATEKYO青森です。
今回は前回の続きとして、小論文の書き方についてもう少しだけ掘り下げてみます。
前回で定言命法と仮言命法について述べました。
例えば「環境に配慮しなければならない」というのは、現代においてはほぼ定言命法と化しています。
本来は「生物多様性を守りたければ、環境に配慮する必要がある」や「将来世代に負担をかけない為には、環境に配慮しなければならない」という仮言命法の形を取っていたと思いますが、
その概念が人口に膾炙した結果、今ではほぼ無条件に環境への配慮が是とされ、環境に負荷をかける事は非とされています。
こういった事、或いは自身の中でこのように無条件に是非が決定していることについて論ずる時は注意が必要です。
言うまでもなく、小論文は「論ずる事」が目的な訳ですから命題は仮言命法の形を取るべきです。
一定の論拠、条件の上でその事象に対しての価値判断を下す事が必要です。
ところが自分の価値観の中で既に定言命法化されてしまっている事象について論ずるときに、多くの生徒さんは論拠をしっかりと示さずに価値判断をしてしまう傾向にあります。
「環境に悪いから良くない」「嫌がる人も出てくるから良くない」といった形で、浅い根拠で主張を繰り広げてしまう事がままあります。
その事柄が、自分にとって自明なこと程その論拠が薄くなってしまう原因はここにあると思います。
こんな時に私が生徒さんに掛ける言葉があります。
「自分が常識だと思っている事を先ず疑いなさい」です。小論文は何も奇抜な論、突飛な発想を誇るためのものではありません。
例え当たり前の結論、多くの人が感ずるままの結論であったとしても、その結論に至るまでの筋道がしっかりしていれば評価されるでしょう。
ですから、(自分にとって)当たり前の常識であったとしても、その論拠や筋道はしっかりと考えロジックを組み立てて書き上げる様にしましょう。
書いた人:むつ事務局 S
青森県で中学受験、高校受験、大学受験、受験予備校といえばKATEKYO学院!
学習相談は時期問わず、いつでもお受けしておりますので、
まずはこちらからご相談ください。