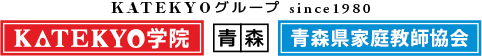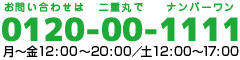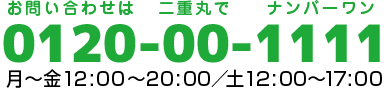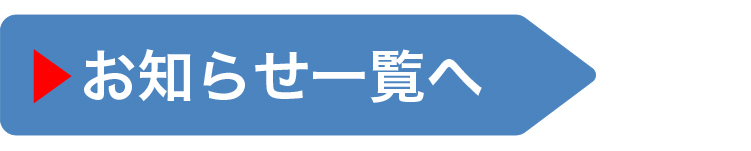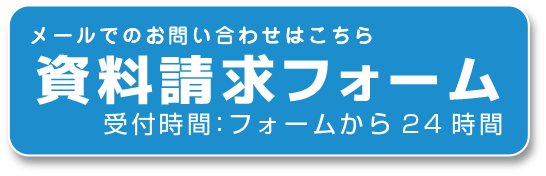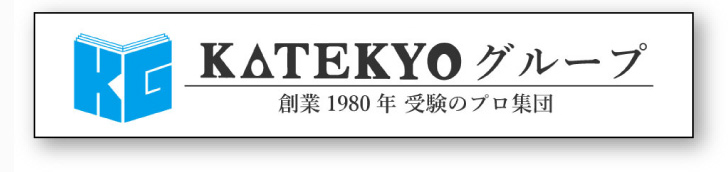KATEKYO学院青森からのお知らせ

2024年5月18日
【大学受験】論理的思考のヒント♯1 「分析と総合」【現代文】
皆さんこんにちは、青森県家庭教師協会・KATEKYO青森です。
本日は青森浪打校教務主任の直井がお話をさせていただきます。
前回の記事をお読みいただきありがとうございました。
連載記事のHP内上位ビューをいただけました。感謝しています。
(前作:【大学受験】論理的思考のススメ【現代文】)
今回から、論理的思考の入口となる考え方、モノの見方をご紹介させていただきます。
月1回更新とはなりますがお付き合いいただけると幸いです。
さて、近代以降、私たち人間は科学技術のめまぐるしい進歩の恩恵を享受している。
その科学技術の発展には「合理主義」という考え方がベースにあり、その思考の礎を築いたのがフランスの哲学者、ルネ・デカルトだ。
デカルトの著書に「方法序説」というものがある。
「我思う、故に我在り」という言葉はあまりにも有名だ。
この書は厚さの割に数多の金言があるので、ぜひ機会があれば読んでみてほしい。
今日はその中から、「分析と総合」という思考法を紹介する。
「三角形の内角の和は180度」という事実は、
私たちは小学年生のときに習った事実で、図形的証明によって明らかである。
このことを学んだ好奇心旺盛な小学生は次のようなことを考える。
「じゃあ四角形の内角の和は何度なんだろう?」
これをもちろん知識として「四角形の内角の和は360度」と覚えてもいいが、
少し賢い小学生は、四角形に補助線を引き、2つの三角形に分割する。
そして、「三角形が2つだから、180×2で360度なんだ」と結論づける。
この作業は、五角形、六角形、、、と増やしていっても対応可能で、
やがて「N角形の内角の和は180(N-2)度」と一般化できてしまう。
こういう思考法が、デカルトの「分析と総合」の1例だ。つまり、
・三角形の内角の和は180度である。
・N角形には1つの頂点から対角線を(N-2)本引くことができる。
・その結果、N角形には三角形が(N-2)個含まれていることがわかる。
と「分析」を重ね、
これらを「総合」して「N角形の内角の和」の定理を導くのだ。
デカルトの提示した「分析と総合」という思考の枠組みの中で、近代科学は発展していく。
ニュートンはニュートン力学を体系化し、物理学の基礎を築いていったのだ。
我々が論理的文章を読み解いていくとき、段落ごとに「分析」をしていく。
もっと言えば、「文」「文節」「単語」にまで分解をして「分析」をすることがあるだろう。
そこから得られた知見を「総合」して筆者の論理をつかんでいく。
現代文を闘うキミはきちんと「分析」ができているか?
そしてそれだけでなく最後に「総合」しているだろうか?
「分析と総合」という思考は合理性を読み解く重要な考え方で、この発想がキミの読解を助けてくれるはずだ。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
書いた人:青森東事務局 直井
青森県で中学受験、高校受験、大学受験、受験予備校といえばKATEKYO学院!
学習相談は時期問わず、いつでもお受けしておりますので、
まずはこちらからご相談ください。