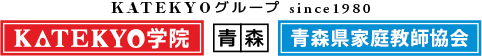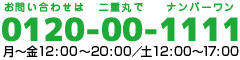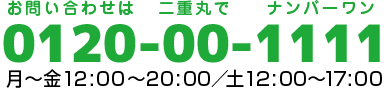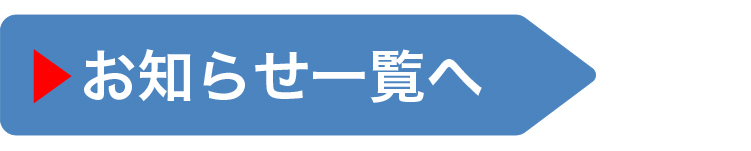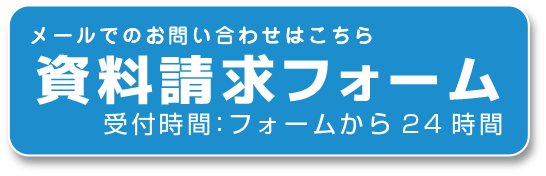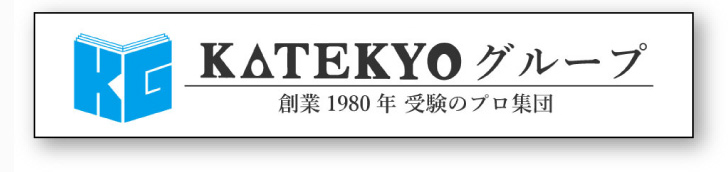KATEKYO学院青森からのお知らせ

2024年9月27日
指示薬
皆さんこんにちは、青森県家庭教師協会・KATEKYO学院です。
皆さんは実験を通じて色々な「指示薬」に出会います。定期テストや入試に出る重要なものを押さえる必要があります。そこで、中学理科に出てくる指示薬についてまとめてみたいと思います。
指示薬とは、特定の物質又はある性質をもつ物質を検出し、反応するもののことです。つまり、得られた物質が何かを確かめたいときに使う薬品のことを言います。
それでは具体的に見ていきましょう。
・リトマス試験紙 青色と赤色の2種類あり、色が変化することで、酸性、アルカリ性を調べることができ、中性では色は変わりません。
・BTB溶液 元々青色をしていてアルカリ性の状態で保存されています。アルカリ性→中性→酸性と変化していくと、青色→緑色→黄色と変化します。
・塩化コバルト紙 水を含むと、赤色に変化する性質を利用して、水が含まれているかを調べます。水に触れると、青→赤(桃)。炭酸水素ナトリウムの熱分解で出てくるよね。
・フェノールフタレイン液 元々は無色透明ですが、アルカリ性に反応して赤色に変化します。アルカリが強くなるほど、濃い赤色になります。アンモニアの発生とか炭酸水素ナトリウムの熱分解で出てくるよね。
・石灰水 二酸化炭素を調べるときに使います。無色透明ですが水酸化カルシウムという白い個体が溶けています。白く濁る反応は、中和反応になります。
他にも生物分野で出てくる、デンプンを調べるためのヨウ素液、糖を調べるためのベネジクト液、核や染色体を赤く染める酢酸カーミン液(酢酸オルセイン溶液)など、ありますよね。
一度、自分なりに変化やどの実験で使用するか、整理してみてはいかがでしょうか。
書いた人:むつ事務局 まさ獅子
青森県で中学受験、高校受験、大学受験、受験予備校といえばKATEKYO学院!
学習相談は時期問わず、いつでもお受けしておりますので、
まずはこちらからご相談ください。