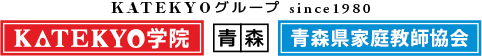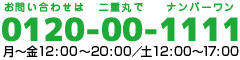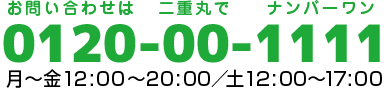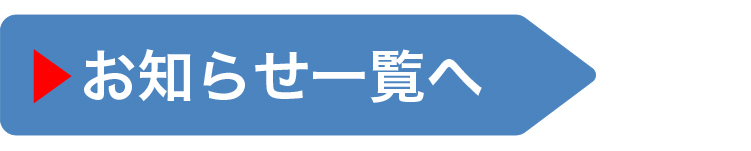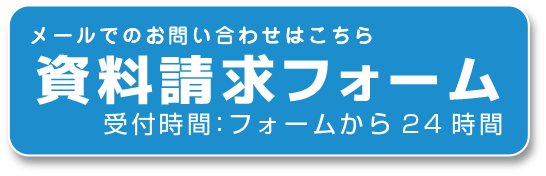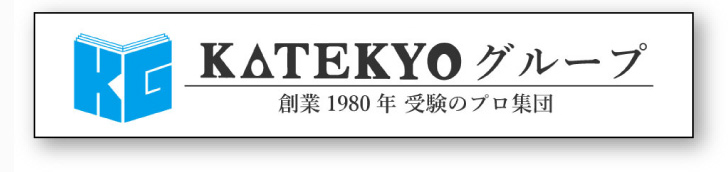KATEKYO学院青森からのお知らせ
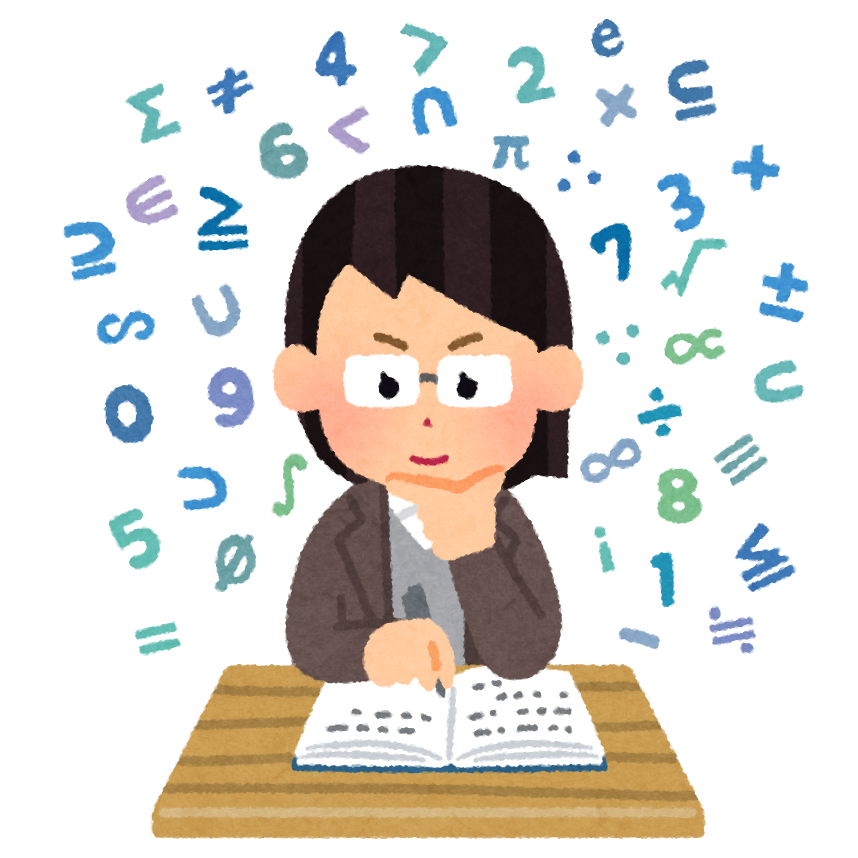
2025年8月20日
数学ⅡBC
皆さんこんにちは、青森県家庭教師協会・KATEKYO青森です。
いまいちそのネーミングの収まりの悪さに慣れない数学ⅡBCはそれもさることながらその内容、そして試験時間も変更され新課程の中でもわりと変更点の多い科目になったように思います。必答問題は三角関数、指数・対数関数、微分・積分と例年と変わらない感じですが、問題は選択問題の新課程で新たに追加された統計的推測と複素数平面でしょう。例年通りのベクトルと数列に合わせて4題から3題を選択するということは自ずと新課程問題を少なくともひとつ取り組まなければならない。ただここはひとつみなさん、そんな消極的な態度をいったん留保しあえて新しく出題されたこの2分野に勇気をもって臨んでみるというのもありなのではないかとわたしは思うのです。というのもこの2分野、取り組んでみますと割と解きやすいというかベクトル数列よりも点数がとりやすいのではないかと思うところもあるのです。複素数平面の問題は基本的な複素数の計算と実軸と虚軸、共役な複素数の位置関係、絶対値、あとは設問の文章が誘導してくれるのでおそらく複素数平面で習う前半部分の知識だけで解けてしまう問題だったように思われましたし、統計的な推測問題では正規分布表の使い方を知ってこれもまた設問の誘導にしたがって推定から最後は仮説検定という流れは学校の定期考査の学習がしっかりできていれば充分対応可能な問題だったとも思うのです。これらは新分野のはじめての出題ということへの配慮という面もあるでしょうし、過去問題が少なく対策しづらいからという理由もあるのでしょう。この傾向は数学ⅠAでも顕著で、もう何十年と出題されている図形の計量などの問題は馬鹿正直に計算してたら明らかに時間が足りなくなるので解き方をスライドさせてある程度答えの見通しがたったら切り上げるなどといったテクニックが必要だったり、はたまた出題しすぎてもはや文学的というか哲学的ともいえる分散の問題とかよりならば期待値の方が割と解きやすい問題になってたりしますのでみなさん、数ⅡBC選択問題は新分野の問題に積極的に勇気をもって取り組んでみるというのもおすすめいたします。
書いた人:三沢事務局 ぬまけん
---------------------------------------------------
↓お近くの教室はこちらからお探しください↓
青森古川校(青森事務局)のトップページはこちら
弘前駅前校(弘前事務局)のトップページはこちら
本八戸駅前校(八戸事務局)のトップページはこちら
十和田校(十和田事務局)のトップページはこちら
五所川原駅前校(五所川原事務局)のトップページはこちら
むつ新町校(むつ事務局)のトップページはこちら
三沢校(三沢事務局)のトップページはこちら
青森浪打校(青森東事務局)のトップページはこちら
黒石駅前校(黒石事務局)のトップページはこちら
青森観光通り校(青森中央事務局)のトップページはこちら